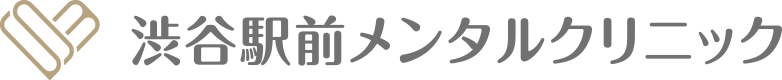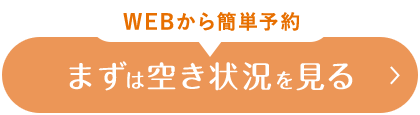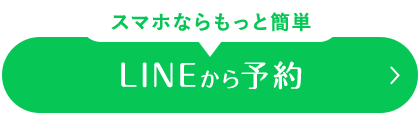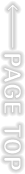自立支援医療制度について
精神障害者自立支援制度について
当院は「精神障害者自立支援制度」の指定医療機関です。
概要
心療内科・精神科領域の疾患の治療は、定期的で継続的な通院医療を必要とすることが多く、医療費もかさむことがあります。
そこで経済的負担を軽減し、医療を受けやすくするために、通院医療費(診察・検査・薬にかかる費用)の1部を公費で負担する制度(障害者自立支援制度[精神通院])があります。この制度を利用されますと、保険の種類に関係なく、10%の自己負担で済みます。(毎月の自己負担の総額も所得により上限があります)
利用の申請
支給を受けるには一定の条件があり、医師の診断書が必要となります。ご希望の際は医師、もしくは受付にお尋ねください。
当院にて作成した診断書とその他の必要書類をそろえて、市町村にてお手続きを行います。また、申請の際に利用する医療機関と薬局の指定が必要となります。
(指定した医療機関と薬局でのみ、1割自己負担となります)
申請後
お手続きを行った日から1割自己負担となります。その後は診察の都度、交付された「自立支援医療受給者証」を受付にご提示ください。
有効期限は1年間です。必要な方は毎年継続のお手続きを行ってください。
(医師の診断書は2年に1回必要となります) その他ご不明な点は受付スタッフまでお気軽にご相談ください。
精神障害者保健福祉手帳制度について
精神障害者保健福祉手帳は、初診から6か月以上経っても日常生活・社旗生活に一定以上の成約がある方が、自立した生活と社愛参加を支援する制度です。
日常生活や社会生活での師匠の程度に応じて、1級から3級の障害等級に分けられます。
- 1級:最も重い障害があり、常に介護が必要な場合など
- 2級:日常生活に相当な支援が必要な場合
- 3級:生活や社会活動にある程度の支障があるが、ある程度の自立が可能な場合
等級によって、受けられる支援や割引の内容が異なる場合があります。
手帳保持者が受けられる支援は、公共料金の割引、税金の控除・減免、障害者雇用枠での雇用、公営住宅への優先入居 などがあります。
当院では、対象となる方に、精神障害者保健福祉手帳を受給のための診断書発行を行っております。お気軽にご相談ください。
精神障害年金制度について
精神障害者年金制度は、精神疾患によって日常生活や仕事に支障が出ている方が対象となる年金給付制度です。この制度は、精神的な障害が持続的である場合に、社会的な支援の一環として経済的な援助を提供することを目的としています。
精神障害者年金は、精神疾患により日常生活や就労に支障があると認められた方が対象です。具体的には、統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害などが対象となり得ます。
支給を受けるには、次のような条件を満たす必要があります。
- 障害年金の受給資格がある場合(年金加入期間中に初診日があること、対象となる精神疾患について初診日から1年6か月以上経過していること など)
- 障害の程度が年金制度で定められた一定の基準に該当すること
- 主治医や医療機関の診断書や、日常生活の状況を記した書類などが必要です
精神障害者年金は、障害の重さに応じて等級が分かれています。等級によって、支給される年金の金額が異なります。一般的には「障害等級1級」「障害等級2級」「障害等級3級」に分けられます。
精神障害者年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
- 障害基礎年金(1級と2級のみ):自営業者や学生など、国民年金加入者が受給できるものです。
- 障害厚生年金(1級から3級):会社員や公務員など、厚生年金加入者が受給できるものです。
当院では、対象となる方に、精神障害者年金受給のための診断書発行を行っております。お気軽にご相談ください。
各種書類・診断書のご案内
就労に関する書類
休職(休学)診断書
休職(休学)をして療養に専念する必要性を医師が証明する診断書
復職診断書
休職中の人が就労可能と医師が判断したことを証明する診断書
傷病手当金申請書
傷病手当金は、病気で働くことが困難となったときに、健康保険から支給される手当です。主治医記載欄に主治医が必要項目を記載します。
ハローワーク用主治医意見書・傷病証明書
ハローワークでの求職活動や雇用保険手続きにおいて、医師による「主治医意見書」や「傷病証明書」が必要となる場合があります。以下に、それぞれの概要と取得方法を説明します。
主治医意見書は、精神障害をお持ちの方がハローワークで求職登録を行う際に、症状の安定性や就労可能性を医師が評価・記載する書類です。これにより、ハローワークは適切な職業紹介や支援を提供できます。
傷病証明書は、求職者が病気やケガにより就労が困難であることを医師が証明する書類です。雇用保険の傷病手当の申請や、求職活動の一時中断を正当化する際に使用されます
雇用保険に加入している人が失業してハローワークで休職活動をするときには、雇用保険の基本手当(失業保険)を受け取ることができます。病気などによる就労困難な理由がある場合、ハローワークに主治医意見書や傷病証明書を提出し申請すると最大3年間受給することが可能になることがあります。
ハローワーク用就労可能証明書
求職者が就労可能な状態であることを医師が証明する書類です。この証明書は、雇用保険の受給手続きや就職活動において必要となる場合があります。
雇用保険の受給: 病気やケガで雇用保険の受給期間を延長した後、再び就職活動を開始する際に、就労可能であることを証明するために提出します。
就職活動: 企業への応募時に、健康状態を証明するために求められることがあります。
制度申請に関する書類
当院では
- 自立支援医療制度申請用診断書
- 精神障害者保健福祉手帳申請用診断書
- 精神障害者年金制度申請用診断書
を扱っております。気楽にご相談ください。
これらの制度の詳細は各種制度をご参照ください。
また、各種診断書料金については、料金をご参照ください。
なお、当院では初診での下記診断書の発行はお取り扱いしておりませんので、ご了承いただきますようお願いいたします。
- 警察提出用診断書:警察・公安委員会に対して精神疾患が無いことの証明
- 運転免許に係る診断書:公安委員会に対し、運転能力があることの証明
- 猟銃所持許可申請用診断書
その他、各種制度、各種診断書等については受付までお気軽にご相談ください。
傷病手当金について
仕事をしている中で病気やケガにより仕事を休まざるを得ない場合、傷病手当金を受け取れる可能性があります。この制度は、健康保険に加入している方が病気やケガの治療に専念できるよう、収入の一部を補うためのものです。
うつ病などのこころの病気を再発しないよう治療していくために、しっかりと休養をとることが時に必要となります。しかし仕事を休むことで経済的な不安が強くなり、治療に専念できないことも想定されます
そんな時には傷病手当金制度を利用することを検討してみてください。
1. 傷病手当金とは?
傷病手当金は、業務外の病気やケガで4日以上連続して仕事を休んだ場合に、給与の代わりとして健康保険から支給される制度です。
対象となる条件
- 健康保険の被保険者である(主に会社員)
傷病手当金が支給されるのは、全国健康保険協会(協会けんぽ)または組合管掌健康保険(組合健保)であり、国民健康保険(市町村国保)では、原則として傷病手当金は支給されません(国民健康保険組合については、組合ごとに異なります)。 - 仕事以外の病気やケガで仕事を休んでいる(業務上のケガは労災保険の対象)
- 連続する3日間を含め、4日以上仕事を休んでいる
- 休んでいる間、給与の支払いがない(一部支給がある場合は調整される)
2. 支給される金額
傷病手当金の支給額は、過去12か月間の標準報酬日額の2/3(約67%) です。
💰計算方法
(過去12か月の給与の平均)÷ 30日 × 2/3 = 1日あたりの傷病手当金
3. 支給される期間
傷病手当金は、最長1年6か月間受け取ることができます。ただし、休職を始めた日から1年6か月が経過すると、たとえ病状が続いていても支給は終了します。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
4. 申請方法
- 傷病手当金支給申請書を準備してください。 勤務先の担当者や企業が加入している健康保険組合へご相談してみてください。(一部の健康保険組合のHPからダウンロードできる場合もあります。)
- 医師の証明が必要ですのでクリニックへお持ちください。その際には、申請期間(労務不能期間;いつからいつまでお休みが必要であったか)を勤務先とご相談のうえお持ちください。
- 会社の証明(勤務先に記入してもらう)を受けた後、勤務先の健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請書を提出します。通常、申請から1〜2か月程度で指定口座に振り込まれます。
5. 休職中の注意点と期間延長について
⚠ 1年6か月を超えると支給終了
⚠ 業務中の病気・ケガは対象外(労災保険の対象)
⚠ 失業中や退職後の申請には制限がある(退職後も条件によって受給可)
※ 期間の延長も可能です
経過観察の上、病状によっては 継続してお休みが必要な場合 もあります。その際は、職場へ休職延長の診断書 を提出する必要があります。
1ヶ月以上受診がない場合、診断書を作成できないことがあり、申請が通らない可能性もあります。
しっかりと回復を目指すために、休職中は定期的に通院し、治療に専念しましょう。